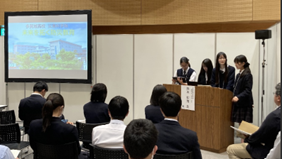2024年10月の記事一覧
【災害科学科】栗駒・気仙沼巡検を実施しました!
1 目的
露頭見学や試料採取に適した県内外のフィールドにおける、地学分野の観察・調査の野外実習を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。また、これまでの学習をもとに岩手宮城内陸地震や東日本大震災の被災地を巡り考察することを通して、防災への意識付けの強化を図る。
(1)基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。
(2)観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。
(3)まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。
2 主催 多賀城高校
3 期日 事前講義:2024年7月5日
当 日:2024年7月24,25日
4 会場 栗駒山麓ジオパークビジターセンター、リアスアーク美術館、
気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館、南三陸ホテル観洋、大谷海岸、小泉海岸、
高野会館、南三陸町旧防災対策庁舎
5 参加者 <災害科学科>2年39名、1年40名
6 実施内容・評価
巡検前に、東北大学学術資源研究公開センター教授の高嶋礼詩様より事前講義をいただき、岩手・宮城内陸地震による栗駒山の地すべりのメカニズムについて学習しました。巡検当日は、栗駒および気仙沼の過去の災害について実際に足を運んで本物を感じながら学ぶことができました。気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館では、気仙沼向洋高校の生徒さんに語り部を行っていただき、当時の気仙沼の状況を知るとともに、本校で行っている「津波伝承まち歩き」の参考にさせていただきました。また、事後学習では、巡検でもっとも考えさせられたことから防災・減災に関する課題と解決策、さらにはその解決策を実現するための社会的障壁まで考えました。巡検で学んだことは、災害科学研究のテーマ設定等に生かしていきます。
7 生徒感想
私が今回の巡検で最も考えさせられたのは、これからの人たちに震災のことを伝承していくことの大切さです。理由は、巡検に行く前の私は「どうして東日本大震災を思い出したくない」という人がいるのにも関わらず、なぜ震災遺構を残しているのだろうと思っていました。しかし、残している理由として、「被災した場所を残すのは心が痛いが、これからの人に伝えていくには大切なことだし津波の破壊力や高さを知ってもらいたい」「この場所でどのような行動をとって命が助かったのかを知ってほしい」などと言った震災を経験した人たちの思いがあると思いました。私自身今回の巡検を通して、映像だけじゃ伝わってこない津波の恐ろしさや恐怖を実際にその現場を訪れたことによって感じることができました。
また、私は東日本大震災が起きた時はまだ2歳で何も記憶にありませんでしたが、家族からの話今回のような巡検を通して当時の状況を多く知ることができました。このようにして、自分が伝承してもらった分、次の人へどんどん伝承していきたいと思いました。 (災害科学科1年 鈴木蓮)
「震災対策技術展」東北ー自然災害対策技術展ー に参加してきました
1 目 的
地震、津波等の災害対策技術・製品を自治体、企業、そして一般の方々に広く情報発信することで、減災社会の構築に寄与し、防災産業の発展に貢献することを目的とする技術展に参加し、本校の防災・減災・伝災への取組を広く発信するとともに、他団体の内容を生徒の探究活動や今後の連携に活用する。
2 日 時
令和6年5月21日(火) ポスター展示
22日(水) 10:00~17:00 ポスター発表、口頭発表
3 場 所 仙台市中小企業活性化センター(AERビル5階)
4 参加者 災害科学科 (2年生5名、3年生4名)
5 実施内容・評価
第12回「震災対策技術展」東北にて災害科学科2年生5名、3年生4名が災害科学科の防災・減災・伝災についての取り組み紹介や生徒課題研究の成果発表を行って参りました。課題研究の成果発表では「身近なダンボールベット」と「伝承と防災教育」をテーマに、日頃から意識できる防災・減災についての取り組みを一般の方々に情報発信することができました。災害科学科への注目度は高く、多くの来場者からの声をかけていただき、生徒たちはより一層学習意欲を高めている様子でした。
生徒感想(災害科学科3年 阿部 春佳)
この震災対策技術展では、災害科学科についての発表をすることだけでなく、周りの企業の方の展示を見ることもでき、防災について学びを深めるとても貴重な機会となりました。私は「災害を自分ごととして捉えてほしい」というワードを何度も発表の中で使い、それに関する感想や意見もいくつかあり、とてもやりがいを感じました。高校生という若い世代が大人の方へ働きかけるという機会は必要不可欠だと改めて実感し、今回の経験を今後の防災活動の糧にしていきたいと思いました。
関西大学による模擬講義
1 目 的
災害科学分野に関する大学の模擬講義を聞くことで、自分の進路について考えを深化させるとともに、明確な進路目標設定の一助とする。また、入試制度についての理解を深め、目標達成のために行うべきことを確認し、学習に主体的・継続的に取り組む意識づけをする。
2 日 時 令和6年5月21日 (火) 14:20~17:00
3 場 所 本校 iRis Hall
4 対 象 災害科学科 1年(40名)・2年(40名)・3年(37名) 計117名
5 実施内容・評価
災害科学科1年生から3年生を対象に、関西大学教授陣による災害科学分野に関する模擬講義が実施されました。平野義明教授による生体材料化学、高橋智幸教授による津波・高潮・洪水等の水災害に関する講義では、社会のニーズと研究におけるシーズをどのように結びつけるのか、研究の目的とプロセスについての実例を紹介していただきました。大学レベルの講義を聴講することで、将来自分が学びたいと考えている分野の研究成果が社会でどのように役立っているのかを知ることができ、生徒が自身の進路について考えを深化させる良い機会となりました。