SSH第Ⅱ期1年次(2023)
SS先端研究研修Ⅱ「関東研修」を実施しました!
【目的】
理系生徒を対象に、先端科学・技術の一端を、大学や研究機関における見学や実験実習を通して理解を深めることを目的として行った。また、女性の研究者や大学院生との交流を図り、女子生徒の見識を広げ、将来像としての研究者を意識させる。
【日程】
令和5 年7 月26 日(水)・27 日(木)
【参加生徒】
第2 学年 普通科理系(6 名)および災害科学科(4 名) 計10 名 (女子8 名、男子2 名)
【講師】
東京海洋大学
海洋資源環境学部海洋環境科学科 海底科学(地球科学)研究室 教 授 山中寿朗 氏
海洋生命科学部食品生産科学科 食品保全化学研究室 教 授 後藤直宏 氏
助 教 田中誠也 氏
海洋資源環境学部海洋資源エネルギー学科海洋地盤工学研究室 教 授 谷 和夫 氏
准教授 野村 瞬 氏
海洋資源環境学部海洋資源エネルギー学科デバイス工学研究室 教 授 井田徹哉 氏
東京農工大学
農学部 環境資源科学科水環境保全学/有機地球化学研究室 教 授 高田秀重 氏
講 師 水川薫子 氏
【実施内容・評価】
新たに本年度より、生物や地球環境分野に焦点を当てた研修を企画した。生物や地球環境分野の先端研究に触れ見識を広げることで多様な進路を模索し、研究者像をイメージできる研修にするため内容を精査し、東京海洋大学と東京農工大学の協力を得て本企画を実行することができた。
SS野外実習Ⅰ「浦戸巡検」を実施しました!
【目的】
路頭見学や試料採取に適した県内のフィールドにおける、地学・生物・化学分野の観察・調査の野外実習
を通して、私たちを取り巻く地球環境を理解する。
⑴基礎的な観察・調査・試料採取の方法を学ぶ。
⑵観察記録をもとに、結果をまとめる手法を学ぶ。
⑶まとめから新たな課題を設定することを学ぶ。
【日程】
7 月7 日(金):事前学習
7 月13日(木):野外実習
7 月14日(金):事後学習
・1~3 校時 指導助言「研究成果のまとめ方 図式化のすすめ」
・4 校時 講話「塩竈市浦戸諸島 東日本大震災の体験を振り返って」
【参加生徒】
第1 学年 災害科学科 40 名
【講師】
国立研究開発法人 海洋研究開発機構 海域地震火山部門 上席研究員 田村芳彦 氏(事前学習~事後学習)
一般社団法人浦戸自主航路運営協議会 理事長 内海春雄 氏(事後学習の講話)
【実施内容・評価】
寒風沢島では講師による講義を行った。実際に対岸の野々島を眺め、地層や地形について学んだ。その後、地学班・化学班・生物班に分かれ、野々島へ移動し、フィールドワークを実施した。地学班ではクリノメーターを用いて、地層の走向と傾斜を測定する手法を学んだ。また、島という特殊な地形ならではの特徴や歴史について学んでいた。本巡検を通して、浦戸諸島で体験的に学習したことをレポートにまとめ、課題研究のイメージをつかむことができた。
【SS科学部】学都 仙台・宮城サイエンス・デイ2023に参加しました!
【日時】令和5 年7 月16 日
【場所】東北大学川内キャンパス・東北大学工学部
【発表テーマ】砂浜のマイクロプラスチックをさがしてみよう!
【内容】科学の芽である「ふしぎだと思うこと」を県内の砂浜の砂からマイクロプラスチックを探し出す体験をきっかけに体感してもらう企画を実施した。SS 科学部の生徒がファシリテーターとして、地域の子どもたちやその保護者の方とともに、探し出したマイクロプラスチックから様々な問いを導き出した。
【表彰】東北経済産業局知的財産室長賞、「E」でしょう!
SS地域防災活動(宮城海上保安部と日本赤十字社宮城県支部との合同訓練)
【日時】令和5年7月12日(水)11:30~17:00
【場所】貞山ふ頭、石巻湾
【参加生徒】第1、2学年 災害科学科 20名
【内容】
宮城海上保安部の方々と巡視船ざおうに乗り、船内の様子や、傷病者吊り上げ訓練を見学した。また、大規模地震発生時における被災者の救助の訓練に、トリアージでの傷病者役として生徒は参加した。災害時の初期対応や救助活動について、直接の体験から学ぶことができたとともに、隊員の方々に質問する機会もあり、課題発見や進路意識の醸成につなげることができた。
自然災害共同研究(有珠山)
【目的】
災害科学科の学習充実として、日本で唯一噴火予知が行われた有珠山での野外実習を行う。災害を科学的視点から学ぶにあたり、災害の一つである火山のメカニズム、地域被害の理解に努める。なお、この実習は北海道室蘭栄高等学校が地域巡検として位置付け、本校の生徒と教員を受け入れて行うものである。
【共同校】
北海道室蘭栄高等学校(元SSH指定校)
【参加生徒】
第2学年 災害科学科 3名
【講師】
北海道室蘭栄高等学校 教諭 阿部英一 氏、北翔大学 横山 光 氏、室蘭工業大学 准教授 安井光圀 氏
【実施内容・評価】
実習初日は、まず北海道室蘭栄高等学校においてスライド資料を使いながら有珠山噴火の歴史や実地調査にあたっての基本的な調査手法について学んだ。続く実習2日目には、北海道室蘭栄高等学校の1年生と共同でユネスコ世界ジオパークにも認定されている洞爺湖有珠山ジオパークにおいて実習を行い、専門家の指導のもとで火山噴火の痕跡の踏査やクリノメーターを活用した断層の調査などを実施。実習3日目には、室蘭工業大学 安居准教授指導のもとで大腸菌からDNAを抽出する実験を行い、微生物についての理解を深めたほか、登別温泉の地獄谷において関係者のみ立ち入ることのできる場所で特別に調査させていただいた。
災害科学科 課題研究
災害科学科2年生の中で,「災害伝承と防災教育」を課題研究テーマとしたグループが,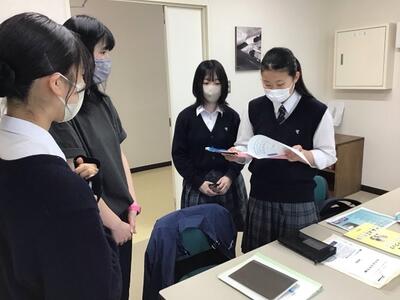
東日本大震災当時の貴重なお話や企業における防災減災への取組を伺いました。
生徒たちは自分たちの学んできたことをもとに,企業の方々にご協力をいただきながら,避難にかかる時間や地形などを科学的な視点から探究しようとしています。これからの研究の発展が期待されます。














